ブリグリのページ
"Solvent Dependent Ultrafast Ground State Recovery
Dynamics of Triphenylmethane Dyes." Yutaka Nagasawa,
Yoshito Ando and Tadashi Okada, J. Chinese Chem. Soc., 47, 699-704,
2000.
"Solvent Dependence of the Ultrafast
Ground State Recovery Dynamics of Triphenylmethane Dyes, Brilliant
Green and Malachite Green." Y. Nagasawa, Y. Ando and
T. Okada, Chem. Phys. Lett., 312, 161-168, 1999.
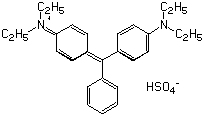 |
 |
|
(以下ブリグリと略します。) |
|
1. 緒言
励起状態から基底状態への無輻射失活は一番単純な一次反応のモデルであり、たくさんの研究がなされてきた。我々の研究の目的は化学反応にどのような溶媒分子の運動や分子振動が関連しているかを解明することにある。トリフェニルメタン(TPM)色素は励起状態の寿命や蛍光の量子収率が溶媒の粘度に依存することで有名な分子である[1-5]。粘度の高い溶媒中で励起状態の寿命が長くなることよりフェニル基の回転運動が無輻射遷移に関与していると考えられている。蛍光寿命や基底状態回復の粘度依存性、反応中間体等の研究が盛んに行われてきた。我々は従来にはない高精度でTPM色素brilliant
green(BG)とmalachite green(MG)のフェムト秒超高速分光を行った。
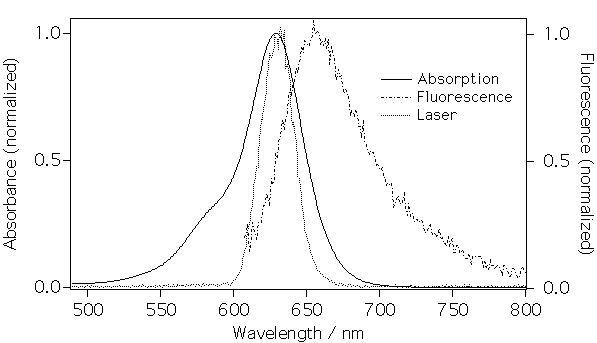
吸収スペクトルとレーザーのスペクトルがきれいに重なってるのが分かります。蛍光スペクトルの強度が弱いのでぎざぎざしてます。
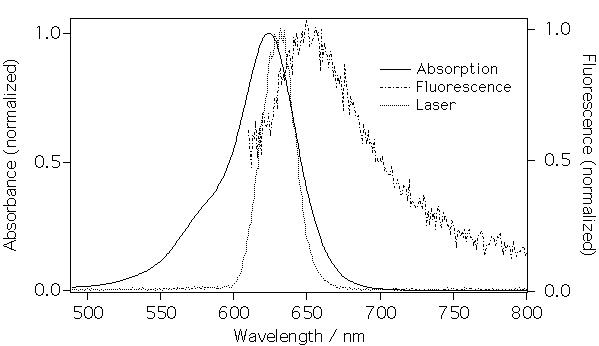
蛍光スペクトルはさらに弱いのでノイズもひどくなってます。このことからマラカイトグリーンの励起状態の寿命はブリグリより短いということが予想できます。
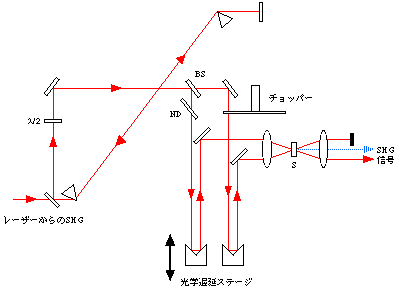
図3 ポンププローブ信号の光学測定系。l/2:半波長板、BS:ビームスプリッタ、ND:ニュートラルデンシティフィルター、S:自己相関関数測定では非線形光学結晶、ポンププローブ測定では試料セル。
2. 実験装置
キャビティダンパーを導入した自己モード同期Cr:forsteriteレーザーの第二次高調波(波長635nm、パルス幅30fs、パルスエネルギー4nJ、くり返し周波数100kHz)で単一波長ポンププローブ(PP)測定の実験を行った。ポンプ光のエネルギーは400pJ程度、プローブ光のエネルギーはその10%でマジックアングルで実験を行った。図3に測定系の模式図を示す。635nmのCr:forsteriteレーザーの第二次高調波はまずパルス幅圧縮用のプリズム対を通過し測定系に導入される。パルスは50%ビームスプリッターでポンプ光とプローブ光に分けられる。半波長板でポンプ光とプローブ光の偏光はマジックアングルにセットする。NDフィルターでプローブ光の強度はポンプ光の1/10にカットする。TPM色素溶液の濃度は0.4mmのセルで光学密度が1.0程度になるように調整した。試料溶液は光照射による劣化を防ぐためペリスタリックポンプで循環させた。光学遅延ステージでポンプ光とプローブ光の時間差を変え、プローブ光のセルの透過光強度をフォトダイオードとロックインアンプで測定した。
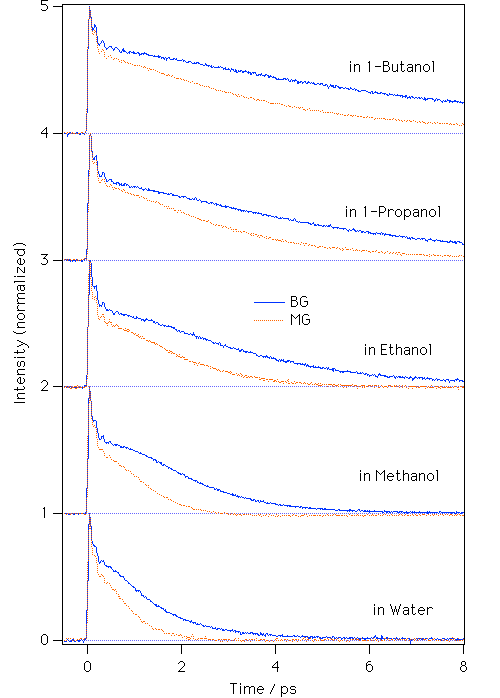
図4 ポンププローブ信号を測定すると励起された分子が基底状態へ戻ってくる様子が観測できます。上の図を見るとブリグリの励起状態の寿命が非常に短いことがわかります。水溶液中では5ピコ秒以内で基底状態に戻ってきますが、ブタノール中では寿命が長くなっています。この分子の励起状態の寿命は溶媒の粘度に依存しているのです。またマラカイトグリーンの寿命は予想どおりブリグリより短いことが分かります。ポンププローブ信号にはブリグリの分子内振動によるクワンタムビートも現れます。シグナルの立ち上がりの部分でうにょうにょっとしてるのがそうです。要するにフェムト秒レーザーを使うと実際に分子が動いてる様子が見えるわけです。We got the beat!!
なぜ、これらの色素の励起状態の寿命は溶媒の粘度に依存するのでしょうか?
一般的な説はここを見てください。
1-c. 実験結果
図4に信号強度の減衰過程を示す。その減衰は溶媒の種類に依存し、水、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールの順に遅くなる。どの信号にもTPM色素の分子内振動による量子ビートが現れている。TPM色素のPP信号の減衰はおもに基底状態の回復を測定しているわけだが、その減衰は単純な指数関数で表現できないことは一目瞭然である。そこで、指数関数で減衰するコサイン関数成分、指数関数的立ち上がり成分、複数の指数関数的減衰成分と自己相関関数とのコンボリューションで信号をフィッティングした。図5にプロパノール溶液の信号とそのフィッティングと残差を示す。非常によいフィッティング結果が得られていることがわかる。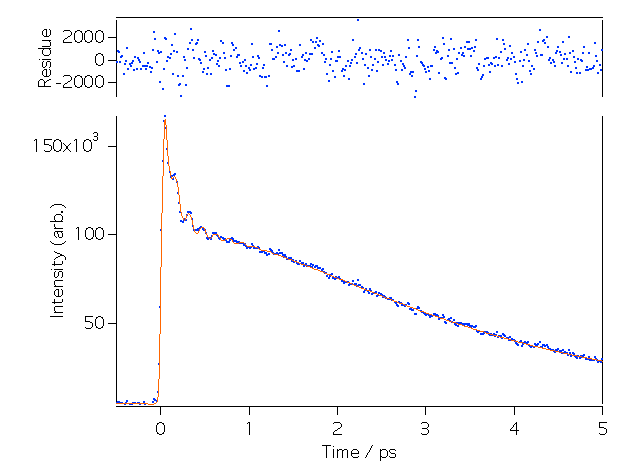
図5 信号をコンボリューションフィッティングして減衰の時定数や振動の周波数を求めます。その結果2つ以上の減衰成分と1つの立ち上がり成分がいることが分かりました。
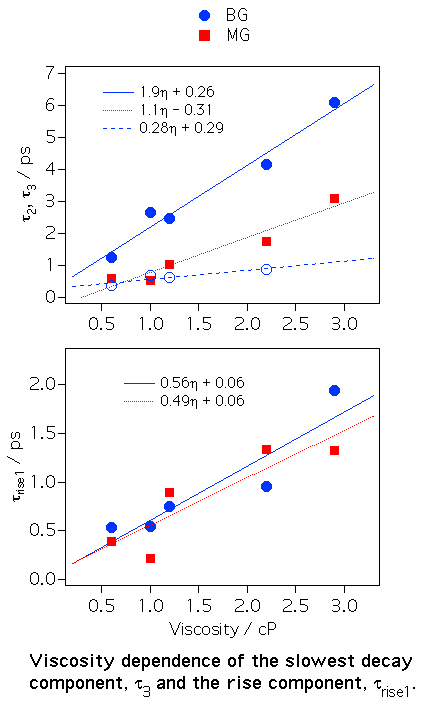
図6 減衰成分と立ち上がり成分の依存性。溶媒が粘っこくなると励起状態の寿命が長くなることが分かります。減衰はブリグリの方が分子サイズが大きいため、遅くなっていますが、立ち上がりはブリグリでもマラカイトグリーンでも同じような時定数で起ることがわかります。つまり立ち上がりは分子サイズ依存性がありません。
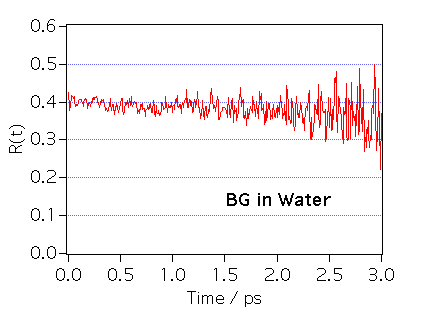
図7 BGの水溶液の異方性解消の経時変化。
3-b. 考察
一般に単色光PP信号には次のような信号が含まれている。
(1)基底状態の吸収の回復。励起状態に上げられた分子が基底状態に戻ってくる様子がおもに観察されるが、このような超短時間領域では系は非平衡状態にあるので単純な絶対反応速度論的解釈は不適当である。この場合、PP法はホールバーニングと同様に励起状態や基底状態での緩和も観測していると考えるべきである。凝縮系での緩和には慣性的な非常に速い緩和と散逸的に起こる遅い緩和があるとされている。信号に現れた約100fsの非常に速い減衰には慣性的な緩和が含まれていると考えられる。従来時間減点付近のスパイクはcoherent
artifactと呼ばれ、人為的な現象として無視されてきた。しかし、現在ではこの非常に速い減衰も分子内や溶媒の緩和現象を含んでいると考えられている。この成分は溶媒にはあまり依存しない。このことは過去の光カー効果やフォトンエコーの実験からも裏付けられている。
(2)蛍光の誘導放出。一般に励起された分子はFranck-Condon状態に留まらず最低励起状態へ緩和する。これは動的ストークスとして時間分解蛍光スペクトルの長波長シフトとして観測される。単色光PP法の場合、時間が経てば蛍光は長波長シフトして観測できなくなるので、誘導放出の寄与は時間が短いほど大きいと考えられる。
(3)誘導ラマン散乱による量子ビート。共鳴ラマン散乱過程により基底状態の振動が励起される現象である。よって今回観測された量子ビートも基底状態のBGの分子内振動がおもに観測されていると考えるのが妥当である。今回観測された量子ビートの振動数や位相緩和時間は溶媒に依存しない。
(4)励起状態の吸収。もし基底状態の吸収と励起状態の吸収が重なっていれば、単色光PP信号にも励起状態の吸収が含まれる。しかし、MGがレーザーの過飽和色素として使用されることからこの可能性は小さいと考えられる。さらに図7のように信号の異方性解消が0.4から始まることもこの考えを支持する。基底状態と励起状態の遷移双極子モーメントの方向は異なっていることが多く、両方の吸収が同時に観測されている場合異方性は0.4から始まらない。
一般に以上のような信号が測定される。減衰が多指数関数的なのは系が熱的に非平衡だと考えれば説明がつく。TPM色素のうちエチレンバイオレットとクリスタルバイオレットの基底状態には異性体があることが知られており、吸収帯の短波長側に異性体の吸収が観測できる[4]。異性化反応の混入により減衰が多指数関数的に複雑になるのだと考えることもできるが、BGには短波長側に吸収が観測されないことから異性体がいる可能性は低いとして議論を進める。
PP信号の減衰成分は我々の測定したアルコール溶液中では粘度に比例することがわかった。図6に一番遅い成分の粘度依存性を示す。BG、MGともに線形な粘度依存性を示すことがわかるが、分子サイズの大きいBGの方が減衰が遅いこともわかる。さらに興味深いことに超高速の立ち上がり成分も粘度に比例する。しかも分子サイズに関係なく、同様な時間領域で起る。このような超短時間領域では溶媒分子のミクロな性質をダイナミクスは反映すると考えていたので、粘度のような溶媒のバルクの性質と相関が得られたということは意外な事実であった。立ち上がり成分は反応中間体の存在を示唆するが、その時定数が粘度に依存することは無輻射失活と同様にフェニル基の回転運動を伴う過程であることを示唆する。しかし減衰成分のように分子サイズに依存しないとはどういうことなのだろうか。第一に考えられることは超短時間領域で起る過程なのでごく限られた角度の回転しかできず、分子サイズに依存しないのではないかという仮説である。またアミノ基のついてないフェニル基の回転が寄与しているとも考えられる。
参考文献
[1] Th. Forster and G. Hoffmann, Z. Physik. Chemie. NF 75 (1971)
63.
[2] D. Ben-Amotz, R. Jeanloz, and C. B. Harris, J. Chem. Phys.
86 (1987) 6119.
[3] E. P. Ippen, C. V. Shank, and A. Bergman, Chem. Phys. Lett.
38 (1976) 611.
[4] D. Madge and M. W. Windsor, Chem. Phys. Lett. 24 (1974) 144.
[5] V. Sundstrum and T. Gillbro, J. Chem. Phys. 81 (1984) 3463.