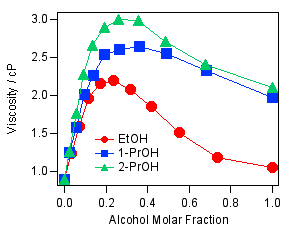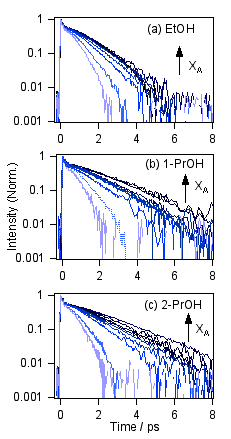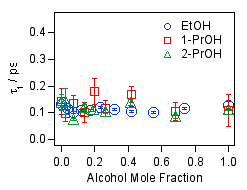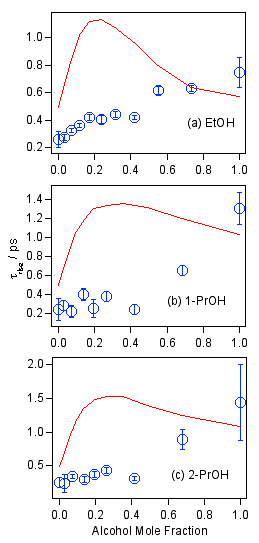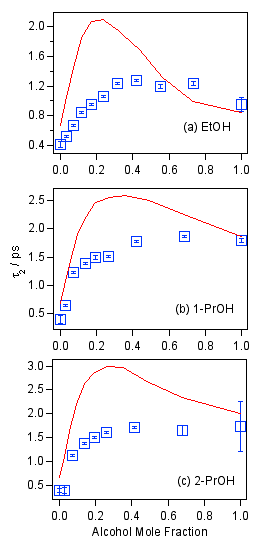"The microscopic viscosity
of water-alcohol binary solvents studied by ultrafast spectroscopy
utilizing diffusive phenyl ring rotation of malachite green as
a probe."
Y. Nagasawa, Y. Nakagawa, A. Nagafuji, T. Okada, and H. Miyasaka,
J. Mol. Struct., 735-736C 217-223 (2005)
砂糖水のお次はアルコール水溶液だ!
というわけで、以下のような実験をしました。
この論文は早稲田時代の恩師である高橋博彰先生の、Journal of Molecular Structure記念特集号に載りました。
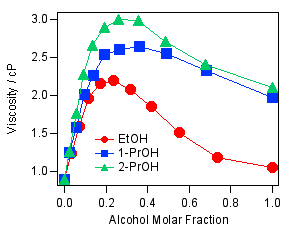
図1
ストーリーは至って簡単。アルコール水溶液のモル分率を変えながら、溶液の粘度を測定すると、粘度はモル分率に非線形に依存することが知られています。図1でエタノール(EtOH)やプロパノール(1-PrOH,
2-PrOH)水溶液の粘度はアルコールモル分率0.2-0.3の辺りで、極大値を取ることがわかります。この現象の説明でよく言われることは、アルコールは水溶液中でクラスターを形成しているということです。疎水性相互作用で集まったアルコール分子の回りを水分子が水素結合してカゴ状の構造を形成するとも言われています。このことを「疎水性水和」と言います。このような構造が一番顕著なのが、モル分率0.2-0.3の辺りで、それ以上アルコール濃度が上がると、クラスター同士が会合し、水分子の水素結合ネットワークによるカゴ状(クラスレート)構造が壊れ、粘度が下がると言われています。
まるで、見て来たような話ですが、本当でしょうか?

図2
そこで、いつものようにマラカイトグリーンを利用して、アルコール水溶液のミクロな粘度を測定することにしました。
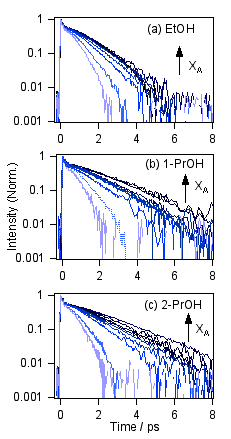
図3
アルコール濃度を上げて行くと、マラグリの励起状態の寿命が長くなり、ポンプ・プローブ信号の減衰が遅くなっていくことがわかります。おもしろいことにマラグリのピコ秒領域での減衰は単一指数関数的であることがわかります。これは、マラグリの回りの溶媒の様子が均一的であることを示しています。もし、マラグリがアルコールクラスターの外と内の両方に存在しているとすると、多指数関数的な減衰になるはずです。そうなっていないということは、どのマラグリ分子を見ても、その回りのアルコール分子の割合はいつも一定であると言えます。
さて、この実験データを解析してみました。
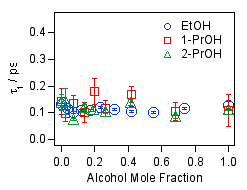
図4
マラグリの減衰には3つの成分がいることがわかっていますが、そのうちの一番速い成分の寿命はほとんどアルコール濃度には依存しないことがわかります。この減衰は100フェムト秒程度と非常に速いので、時間的には溶質分子と溶媒分子が最初に衝突する領域に相当し、ほとんどバルクの粘度は感じていません。
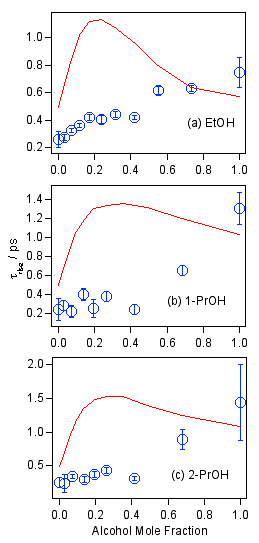
図5
2番目に速いライズ成分と粘度の関係は依然の研究より以下の式で表されることがわかっています。
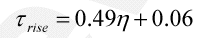
そこで、アルコール水溶液の粘度からこの式で予想したライズ成分の寿命は、図の赤線のようになるはずです。実験結果(青いマーカー)と全然一致していないことがわかります。このライズも2ピコ秒以内という非常に速いタイムスケールなので、溶媒分子との衝突回数は少なく、バルク粘度の依存性は低いようです。
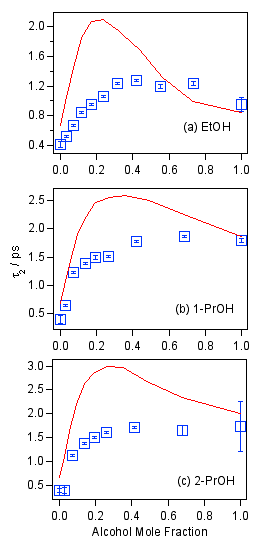
図6
一番遅い成分はマラグリの励起状態の減衰と考えられ、その寿命と粘度の関係は以下の式で表されることがわかっています。
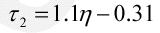
アルコール水溶液の粘度から予想した励起状態寿命は図の赤線のようになるはずです。これまた実験結果(青いマーカー)と全然一致していないことがわかります。実験結果は、モル分率が0.4を越えると寿命が一定になっているように見えます。これは、アルコール濃度が低い場合はマラグリは水分子とアルコール分子の両方に取り囲まれているが、アルコール濃度が上がると、徐々にアルコール分子の割合が増え、モル分率が0.4以上では、ほとんどアルコール分子に取り囲まれていることを示唆するのではないか?と考えています。
んで、結論なんだけど、モル分率0.4以下の低アルコール濃度領域では、水とアルコールがミクロな相分離をしているという積極的な証拠は得られませんでした。クラスターとその周りの「疎水性水和」による粘度上昇もマラグリの寿命にそれほど大きな影響は与えていない。水素結合ネットワーク内に捕らえられ、位置を変えずに回転拡散運動をしてる場合は、巨視的な粘度をあまり感じないようだ。水素結合ネットワークの中をくぐり抜けて並進拡散し、移動していくような場合に限って巨視的な粘度の影響を受けるようになるのかも知れない。
home